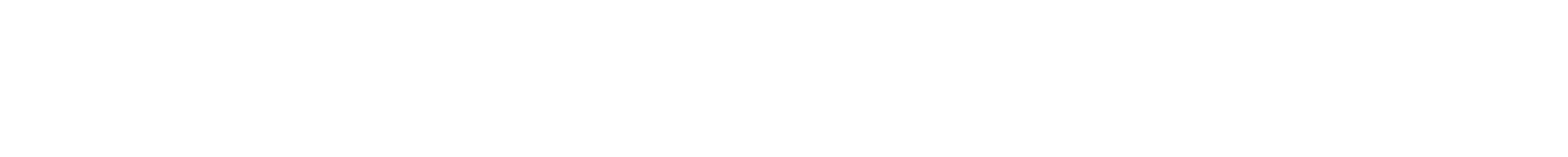神輿「神と人と人」
日本各地では、様々な祭があり、その祭礼に伴い神輿が担がれています。威勢の良い掛け声、或いは静々と、多くの老若男女が集い共に楽しみを分かち合います。
そもそも古代においては、神霊は「坐(ま)す」存在であり、移動するという事はなく、神まつりは、特定の氏族や地域などと深く結ぴついたものでした。自らの意思に依って移動したとされる神として、「続日本記」に天平勝宝元年(七四九年)、聖武天皇発願の大仏建立を助ける為、九州宇佐八幡神は平城京に向かうと託宣され、輿に乗り移動したとされています。又、天慶八年(九四五年)、平安京に東西の国々から神々がやってくるとされ、「志多羅神」等の神々が三基の神輿に乗り、数百名の人々が担ぎ、幣を持ち、鼓を鳴らし舞いながら移動したとされています。この後も同じように神々が輿に乗り移動する、神輿担ぎが定着して現在に続いていくことになります。
只、初期の神々の移動の背景には、自然災害に依る水害、凶作、そして疫病の流行等、人々は自分の暮らしを守るため何とか神々の御守護を頂き、神輿、祭礼を通して社会への不安、大きなストレスを解消する一つ手立てとも考えていたかとも思います。
今現在、お祭りの神輿となると、私たちは担ぐのがびとつの楽しみ、そして恒例行事的な感覚で参加してはいませんでしょうか。本来の神輿は神々のお力を頂き、神々がお通りになることにより、地域の安寧、人々の暮らしの安全を祈り、そして、担ぐ私達も神々の恩頼を頂き、自身の魂の活性化を計り、明日からも力強く生きていこうと思う事ではないでしょうか。神輿担ぎで汗をして人と人が協力し合い、互いに絆を深め、より充実した暮らし、安心して住むことが出来る街を目指し、私達神輿会頓宮は、貢献していきたいと考えております。